Taketsuru Pure Malt
2025.07.01
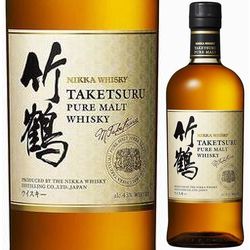
余市と宮城峡が織りなす竹鶴の名を冠した逸品
「竹鶴ピュアモルト」は、日本のウイスキーの父・竹鶴政孝の名を冠した、ニッカウヰスキーを代表するピュアモルトウイスキー(※)です。余市蒸溜所の力強くスモーキーなモルトと、宮城峡蒸溜所の華やかでフルーティーなモルトを絶妙にブレンドし、モルト100%でありながらも驚くほど飲みやすい味わいを実現しています。
⇒ピュアモルトウイスキー(※)
〇「ピュアモルト」とは、100%モルトウイスキーのみで構成されたウイスキーを指します。つまり、大麦麦芽(モルト)を原料とし、単式蒸溜器で蒸溜された原酒だけを使ってブレンドされたものです。グレーンウイスキー(トウモロコシやライ麦などを原料としたウイスキー)は一切含まれていません。
ただし、「ピュアモルト」という呼称は日本独自のもので、国際的にはあまり使われていません。海外では同様のスタイルを「ブレンデッドモルト」または「ヴァッテッドモルト」と呼びます。これは、複数の蒸溜所で造られたモルト原酒をブレンド(ヴァッティング)したウイスキーを意味します。
一方で、「シングルモルト」は単一の蒸溜所で造られたモルト原酒のみを使用している点が異なります。 つまり、どちらもモルト100%ですが、原酒の出どころが「単一」か「複数」かで区別されるのです。 ニッカの「竹鶴ピュアモルト」シリーズは、余市と宮城峡という異なる蒸溜所のモルト原酒をブレンドしており、力強さと華やかさを兼ね備えた味わいが特徴です。要するに、「ピュアモルト」とは“モルト100%”であることを強調した呼び名であり、シングルモルトとは兄弟のような関係。どちらもモルトの魅力を存分に楽しめるスタイルです。
シェリー樽やリメード樽で熟成された原酒が織りなす、なめらかな口当たりと奥行きのある香味が特徴で、バナナやネーブルオレンジを思わせるフルーティーさに、ほのかなピートの余韻が重なります。
グレーンウイスキーを使わずに、複数のモルト原酒のみで調和を生み出すという挑戦は、ニッカのブレンド技術の粋とも言えるもの。まさに、竹鶴政孝が夢見た「本物のウイスキー」を体現した一本です。日常の一杯から特別な時間まで、幅広いシーンで楽しめる、洗練された日本のクラフトマンシップの結晶です。
■飲み方あれこれ!!
〇「竹鶴ピュアモルト」はそのバランスの良さから、さまざまな飲み方で楽しめる万能型のウイスキーです。
ストレート:
香りや味わいをダイレクトに楽しめる基本の飲み方。特に初めて飲むときや、じっくりテイスティングしたいときに最適です。
トワイスアップ(水割り1:1):
常温の水を同量加えることで、香りが開き、繊細なフルーティーさや樽香がより感じやすくなります。
ロック:
氷でゆっくりと温度が下がることで、味の変化を楽しめます。余韻のビターさやピート香が際立ちます。
ハーフロック(氷+少量の水):
ロックよりもまろやかで、香りと味のバランスがとれた飲み方。食中酒としてもおすすめです。
ハイボール:
炭酸で割ることで、竹鶴のフルーティーさとほのかなスモーキーさが爽やかに引き立ちます。食事との相性も抜群。
ホットウイスキー:
寒い季節にはお湯割りで。甘みが引き立ち、やさしい飲み口になります。
▶「竹鶴政孝」のこと
竹鶴政孝(1894–1979)は、「日本のウイスキーの父」と称される実業家であり、ニッカウヰスキーの創業者です。広島県竹原町の造り酒屋に生まれ、幼少期から酒造りの現場に親しみながら育ちました。大阪高等工業学校(現・大阪大学)で醸造を学んだ後、摂津酒造に入社。1918年には本格的なウイスキー製造技術を学ぶため、単身スコットランドへ留学します。
スコットランドではグラスゴー大学や複数の蒸溜所で実地研修を重ね、モルトウイスキーとグレーンウイスキーの製造法を徹底的に学びました。このときの知見は「竹鶴ノート」としてまとめられ、後の日本のウイスキー産業の礎となります。また、現地で出会ったスコットランド人女性リタと結婚し、帰国後も生涯を共にしました。
1923年、鳥井信治郎に招かれて寿屋(現・サントリー)に入社し、日本初の本格ウイスキー蒸溜所「山崎蒸溜所」の設立に尽力。1929年には「白札(しろふだ)」を発売しますが、理想とするスコッチスタイルのウイスキー造りを追求するため、1934年に独立し北海道余市に「大日本果汁株式会社(後のニッカウヰスキー)」を設立しました。
戦時中の困難を乗り越え、1940年に初の製品「ニッカウヰスキー」を発売。以後も品質にこだわり続け、「スーパーニッカ」や「ハイニッカ」などの名品を世に送り出しました。1969年には宮城峡蒸溜所を開設し、東北の自然を活かしたウイスキー造りにも挑戦。1979年、85歳で逝去するまで、日本のウイスキー文化の発展に生涯を捧げました。
その情熱と信念は、今もニッカの製品や「竹鶴」ブランドに息づいています。まさに、夢と技術を融合させた先駆者でした。
▶「竹鶴政孝」の歴史(年表)
1894年:
広島県賀茂郡竹原町に生まれる。竹鶴酒造を営む家に育つ。
1916年:
大阪高等工業学校(現・大阪大学)醸造科を卒業。摂津酒造に入社。
1918年:
スコットランドへ留学。グラスゴー大学や蒸溜所でウイスキー製造を学ぶ(※)。 1920年:スコットランド人女性リタと結婚。日本へ帰国。
⇒グラスゴー大学や蒸溜所でウイスキー製造を学ぶ(※)
〇1919年、スコットランドに留学していた竹鶴政孝は、実地研修の受け入れ先が見つからず、大きな壁に直面していました。しかし彼はあきらめることなく、なんのつてもないままロングモーン蒸溜所の門を叩きます。その熱意に心を動かされた蒸溜所側は、彼を受け入れ、麦芽の製造から蒸溜、貯蔵に至るまで、ウイスキー造りの全工程を体験させました。この貴重な体験は、彼が帰国後に詳細に記録した「竹鶴ノート」として結実し、日本のウイスキー産業の礎となります。
その後、1963年にイギリスの外相アレック・ダグラス=ヒュームが来日した際、この「竹鶴ノート」の存在に触れ、「一人の日本人青年が万年筆とノートだけで、我が国のウイスキー製造技術を持ち帰った」とユーモアを交えて語りました。この言葉は、竹鶴の観察力と記録力、そして揺るぎない探求心に対する最大級の賛辞であり、日本の本格ウイスキー誕生に寄与した偉業を象徴するエピソードとして語り継がれています。
1923年:
鳥井信治郎に招かれ、寿屋(現・サントリー)に入社。
1924年:
山崎蒸溜所の設立に尽力。初代工場長に就任。
1929年:
「白札(しろふだ)」を発売。日本初の本格ウイスキーを世に出す。
1934年:
寿屋を退社し、北海道余市に「大日本果汁株式会社(後のニッカウヰスキー)」を設立。
1940年:
「ニッカウヰスキー」第1号製品を発売。
1952年:
社名を「ニッカウヰスキー株式会社」に変更。
1969年:
宮城峡蒸溜所を開設。東北の自然を活かしたウイスキー造りを開始。
1970年:
北海道開発功労賞を受賞。
1979年:
肺炎のため死去。享年85歳。
■「余市蒸留所」と「宮城峡蒸留所」の違い
〇「竹鶴ピュアモルト」は、ニッカウヰスキーが誇る2つの蒸溜所――余市と宮城峡――それぞれの個性を絶妙に融合させた逸品です。 北海道・余市蒸溜所では、伝統的な石炭直火蒸溜が今なお続けられており、スモーキーで力強く、どこか海の香りを思わせる重厚なモルトが生まれます。寒冷な気候とピートの影響も相まって、骨太で男性的な味わいが特徴です。 一方、宮城県・仙台市に位置する宮城峡蒸溜所では、蒸気による間接加熱が採用され、やわらかく華やかな原酒が造られています。緑豊かな渓谷に囲まれた穏やかな環境が、リンゴや洋梨のようなフルーティーさや、花のような繊細な香りを引き出します。 この両蒸溜所の対照的な原酒がブレンドされることで、深みと飲みやすさを兼ね備えた「竹鶴ピュアモルト」が完成するのです。まさにニッカのブレンド技術の結晶であり、日本のウイスキー文化の粋を体現した存在といえるでしょう。
Data
製造元:ニッカウヰスキー(株)(アサヒビール)
所在地:東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号
URL:https://www.nikka.com/agecheck/permission.html(ニッカウヰスキー公式サイト)
発売年:2000年11月
アルコール度数:43度
容量:700ml
【広告】楽天/ウイスキー通販
【広告】Amazon/ウイスキー通販
・ご指定以外の商品も表示されます。
・お酒は二十歳になってから。
